2015年 夏期休業のおしらせ
2015年8月12日
弊社では下記の期間、夏期休業とさせて頂きます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
夏期休業期間: 2015年8月13日(木)~8月16日(日)
8月17日(月)からは平常どおり営業いたします。
休業期間中も、ウェブからのご注文・お問い合わせは可能ですが、対応は17日以降となります。ご了承ください。
『メトロガイド』2015年9月号にて『伝統野菜の今』が紹介されました
2015年8月12日
日刊工業新聞社のフリー情報誌『メトロガイド』9月号プレゼントコーナーにて『伝統野菜の今』を紹介していただきました。
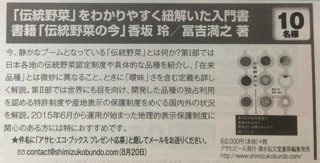
東京メトロ全駅(副都心線除く)にある青いボックスで配布されています。お立ち寄りの際はぜひ探してみてください。
新聞協会報にて『新聞のある町』が紹介されました
2015年8月6日
「新聞協会報」(2015年7月28日、第4155号、日本新聞協会)のコラム「週間メモ」にて『新聞のある町 地域ジャーナリズムの研究』を紹介していただきました。
![]()
読者との距離の近さに痛いほど悩みながら、住民の立場で事実を書く
という表現が、地域紙独特の状況を端的に伝えています。
地域紙ごとに、そうした距離感にも少しずつ違いがあります。それぞれの特色を、ぜひ同書でかいま見てください。
『ガバナンス』8月号にて『伝統野菜の今』が紹介されました
2015年8月6日
月刊『ガバナンス』(平成27年8月号、ぎょうせい)「Reader’s Library」欄にて『伝統野菜の今 地域の取り組み、地理的表示の保護と遺伝資源』を紹介していただきました。

本書は、伝統野菜という概念とその成立背景、今後の産地や知的財産の保護といった議論との関係性を掘り下げようと試みたものだ。
として、個別の事例だけにとどまらない本書の新しい意義を評価してくださっています。
これからの農業を考える一助として、ぜひご一読ください。
あやべ市民新聞にて『新聞のある町』が紹介されました
2015年7月30日

あやべ市民新聞(2015年7月22日号)にて『新聞のある町 地域ジャーナリズムの研究』を紹介していただきました。
地域紙の存在によって「地方行政や議会の透明度が高くなる」という四方さんの指摘などに注目しながら、本全体を概括されています。
あやべ市民新聞は、同書に「京都北部グループ」として収録されている地域紙のひとつで、京都府綾部市を中心とするエリアで活動しながら、近隣エリアの3紙とともに独特な関係性を築いています。
地域紙ならではといえるその興味深い姿を、ぜひ『新聞のある町』でかいま見てください。
大場千景さんが日本文化人類学会奨励賞を受賞
2015年7月25日
大場千景さんが、第10回日本文化人類学会奨励賞を受賞されました。この賞は「無文字社会における『歴史』の構造―エチオピア南部ボラナにおける口頭年代史を事例として」(『文化人類学』第78巻1号、2013年)の業績を対象とするものです。
大場さんの長年にわたるフィールドワークの成果は、受賞対象論文と同時に、『無文字社会における歴史の生成と記憶の技法 口語年代史を継承するエチオピア南部ボラナ社会』(清水弘文堂書房刊)という成果にもつながっています。現代では希少な口誦伝承が残る社会の一端に、ぜひ触れてみてください。
北陸中日新聞にて『伝統野菜の今』が紹介されました
2015年7月23日
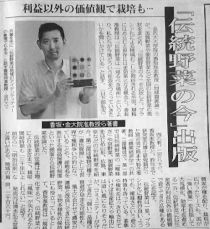
北陸中日新聞(2015年7月20日)にて『伝統野菜の今 地域の取り組み、地理的表示の保護と遺伝資源』を紹介していただきました。
記事では、同書が扱っている幅広いトピックを紹介するとともに、香坂准教授からのメッセージも紹介してくださっています。
「伝統野菜は(……)私たちが今後どういう社会をつくっていきたいかを問いかけている」という言葉のとおり、これからの農業や社会全体の姿を考えさせる一冊です。ぜひご一読ください。
毎日新聞(石川版)にて『伝統野菜の今』が紹介されました
2015年7月23日

毎日新聞(石川版、2015年7月22日)にて『伝統野菜の今 地域の取り組み、地理的表示の保護と遺伝資源』を紹介していただきました。
記事では、香坂准教授のコメントともに、同書が扱っている幅広いトピックを的確に整理して紹介してくださっています。毎日新聞ウェブサイトでも公開されていますので、ぜひご一読ください。
「移民政策研究」Vol.7にて『難民の人類学』が紹介されました
2015年5月28日
移民政策学会編「移民政策研究」2015 Vol.7 書評欄にて『難民の人類学 タイ・ビルマ国境のカレンニー難民の移動と定住』を紹介していただきました。
評者は人見泰弘氏(名古屋学院大学専任講師)。同書の内容を簡潔に紹介し、分析枠組みや難民性の概念に批判的・発展的な問いかけをおこないながら、以下のように締めくくられています。
本書は,カレンニー難民の経験や意識,解釈を読み解き,彼らの移住過程を厚みのある記述をもって描いている。(……)難民研究では数少ない人類学的手法が活かされた著作であり,多くの人に読まれるべき一冊である。
みなさまもぜひご一読ください。
日本経済新聞にて『地球千年紀行 先住民族の叡智』が紹介されました
2015年3月3日

日本経済新聞(2015年2月20日夕刊)「こころの玉手箱」欄・月尾嘉男先生の連載第5回にて、「技術」を追求してこられた月尾さんが疑問を抱き、技術に依存しない社会を取材する活動について語られています。
「技術にそれほど依存しない社会を調べれば、文明社会の未来が見えるかもしれないという思い」が、世界中の先住民族からヒントを得ようとする行動につながったそうです。その活動はテレビ番組となり、また弊社刊『地球千年紀行 先住民族の叡智』など書籍としてもまとめられています。
「子どもの本棚」7月号で『けふはここ、あすはどこ、あさつては』が紹介されました
2014年6月26日
日本子どもの本研究会編集の月間書評誌「子どもの本棚」7月号にて『けふはここ、あすはどこ、あさつては』を紹介していただきました。
山頭火の句とニコル氏の写真と文章が互いに呼び合ったかのような構成になっている。
と評してくださっています。
なお、日本子どもの本研究会では8月にニコルさんを招いての研究集会を企画されています。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。

