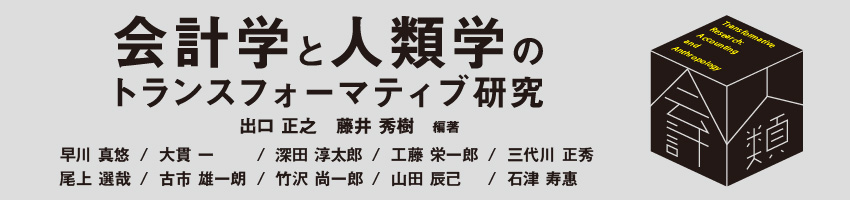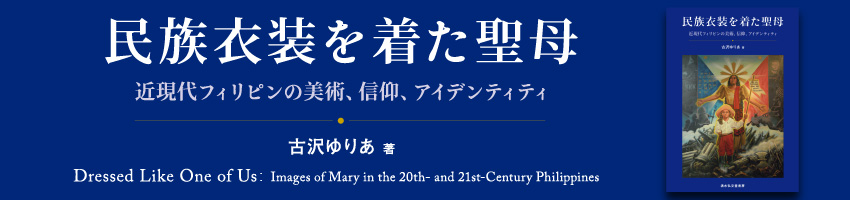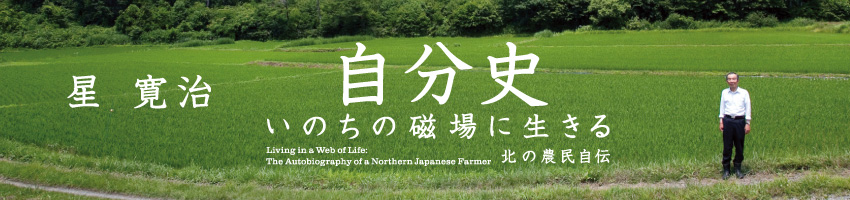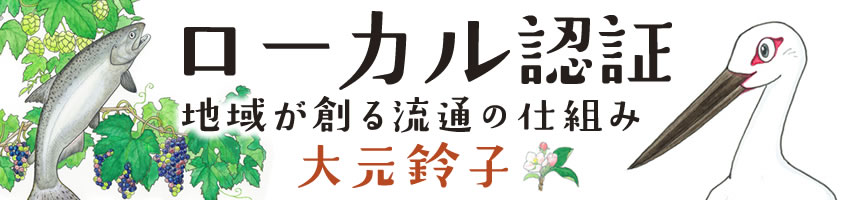ひりつく色

挾土秀平 著 挾土秀平 著者紹介 日本を代表する左官職人が吐露する、思考の痕跡。 体験に裏打ちされた『生きた言葉』が描く色の物語。 土と水と言葉にあやつられたひとりの男。 「見えすぎる眼」をもつ左官が 土のかわりに怯えと […]
極北の大地・グリーンランドの夜明け ―THE FIRST STEPS―

ヌカ・K・ゴッツフレッセン 作・画 沢広あや 訳 岸上伸啓 監修 時は4500年前の北カナダとグリーンランド。復讐をきっかけに、人々は見知らぬ東の地へと赴くことになった。しかし薄い海氷と食料不足に悩まされ、旅は困難を極め […]
士魂 竹内謙の探検人生 【非売品】

竹内 謙 著/竹内 玄 編 ※本書は非売品のためご注文にはお応えできません。ご了承ください。 朝日新聞編集委員から鎌倉市長へ転身し、地方自治の現場を経験。退任後、日本インターネット新聞株式会社を設立し、日本で最初期のネッ […]
難民の人類学 タイ・ビルマ国境のカレンニー難民の移動と定住
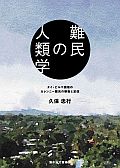
久保忠行 著 「緒言」「目次」ためし読みPDF 問題は、難民というラベルが突きつける固定観念である。 故郷を追われ、難民キャンプや遠く離れた国で暮らす難民たち。ビルマ(ミャンマー)、タイ、アメリカでたくましく生きる姿を丹 […]
早川学校 ほんのちょっとの勇気と知恵でキミは輝く

早川忠孝 著 マジメに生き抜く方法 人とつながり、たくさんの言葉をもらえばいい 東大から自治省を経て弁護士となり、衆院議員時代は「穏健保守」を自称した著者が、人生に役立つメッセージをお届けします。戦直後の長崎での幼少期、 […]
無文字社会における歴史の生成と記憶の技法 口頭年代史を継承するエチオピア南部ボラナ社会

大場千景 著 500年もの間、文字を使わずに語り継がれた歴史。 文字を持たない民族ボラナはどうやって歴史を記憶し、伝えているのか。 物語り、詩、時間、構造とは――。 7年間におよぶエチオピアフィールドワークの集大成 現役 […]
超越国境

安西直紀 著/早川忠孝 監修/日台若者交流会 編 李登輝 激賛! 若者よ 超越せよ!! 台湾元総統 李登輝氏 日台若者交流会 名誉会長就任 特別寄稿掲載! 今こそ、閉塞感を突破する時代! 未曾有の被害をもたらした東日本大 […]
藝術と環境のねじれ 日本画の景色観としての盆景性

早川 陽 著 アサヒ・エコ・ブックス No.36 景色を描くあなたへ。 風景を見るすべての人へ。 日本画は、東洋の「山水」と西洋の「風景」のあいだを揺れ動きつづけてきた。その「揺れ」から生じるオリジナリティ、「盆景性」。 […]
銀座ミツバチ奮闘記 都市と地域の絆づくり

高安和夫 著 アサヒ・エコ・ブックス No.35 高安和夫 著者紹介 自然を身近に感じれば社会が変わる! 銀座ミツバチプロジェクトの中心人物がはじめて語る 銀座の都市養蜂と屋上緑化プロジェクトの舞台裏。 ミツバチが結ぶ大 […]
けふはここ、あすはどこ、あさつては C・W・ニコル×山頭火の世界

C・W・ニコル/南 健二 著 C.W.ニコル・アファンの森財団協力 C・W・ニコル 著者紹介 南 健二 著者紹介 来日50年記念出版! きのうも、きょうも、あすも旅。 1940年、日本中を放浪した俳人はこの世の旅を終え、 […]
融然の探検 フィールドサイエンスの思潮と可能性
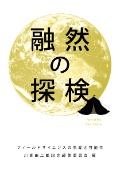
川喜田二郎記念編集委員会 編 岡部聰/米山喜久治/永延幹男/國藤進/三村修/三浦元喜/桑原進/川井田聰/井上敬康/桐谷征一/小島通代/笠松卓爾/丸山 晋/浅井考順/水谷忠資/近藤喜十郎/笹瀬雅史/佐藤光治/青天目利幸/高 […]
地域のレジリアンス 大災害の記憶に学ぶ

香坂 玲 編 大震災の記憶から私たちが学ぶべきことは何か? 私たちに問われている「知」とは何か? BCP(business continuity plan)プランに役立つ1冊! 「レジリアンス」とは何か? いま私たちはこ […]
つぎの4冊