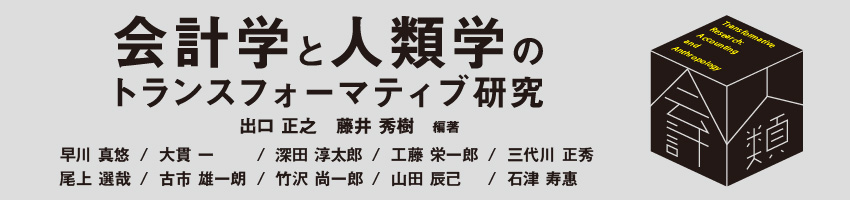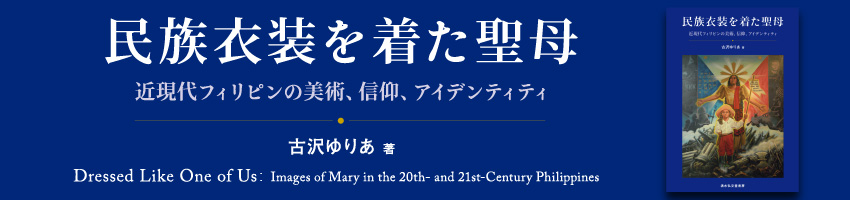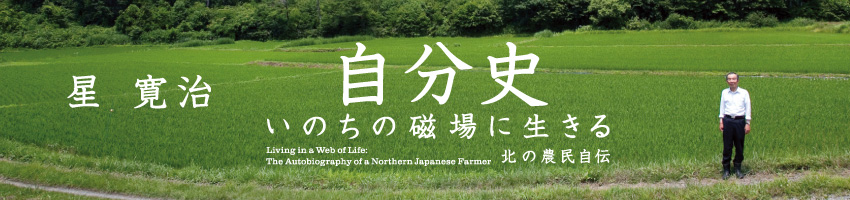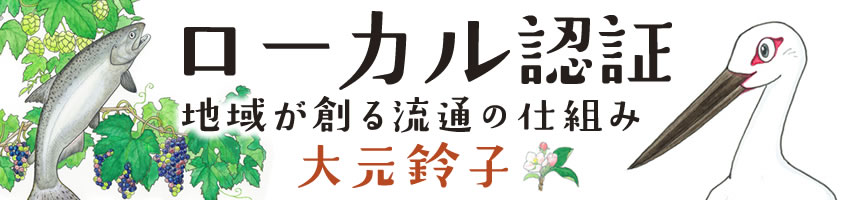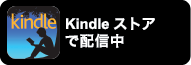難民の人類学 タイ・ビルマ国境のカレンニー難民の移動と定住 Amazon Kindle版
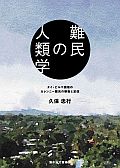
久保忠行 著 ※この商品は Amazon Kindle 専用です。書籍版をお探しの方は『難民の人類学 タイ・ビルマ国境のカレンニー難民の移動と定住』をご覧ください。 ※電子版のため、弊社への直接注文は承っておりません。ご […]
ローカル認証 地域が創る流通の仕組み
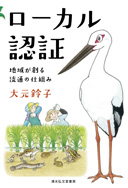
大元鈴子 著 著者紹介 大元鈴子 こちらは紙書籍版の紹介ページです。電子書籍版(Amazon Kindle専用)紹介ページは以下リンクよりご欄ください。 電子書籍版(Amazon Kindle専用)『ローカル認証 地域が […]
環境法の冒険 放射性物質汚染対応から地球温暖化対策までの立法現場から

鷺坂長美 著 著者紹介 鷺坂長美 環境法は、ごみ、公害、環境汚染、自然破壊との闘いの歴史だ。 初めて環境法を学ぶ人に、環境関連法が作られるまでの社会背景や実際の立法過程を、環境省で国会担当も経験した筆者が丁寧に解説。環境 […]
アフリカ美術の人類学 ナイジェリアで生きるアーティストとアートのありかた
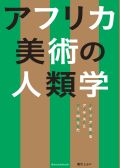
緒方しらべ 著 著者紹介 緒方しらべ 第30回日本アフリカ学会研究奨励賞(2018年度)受賞! ナイジェリア南西部、ヨルバ神話の舞台となる古都イレ・イフェで、たくさんのアーティストがアートなるものを制作して暮らしている。 […]
融然の探検 フィールドサイエンスの思潮と可能性 Amazon Kindle版
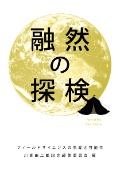
川喜田二郎記念編集委員会 編 岡部聰/高山龍三/永延幹男/國藤 進/三浦元喜/桑原 進/川井田 聰/井上敬康/桐谷征一/小島通代/笠松卓爾/丸山 晋/浅井考順/水谷忠資/近藤喜十郎/笹瀬雅史/佐藤光治/青天目利幸/高橋芳 […]
増補版 宥座の器 グンゼ創業者 波多野鶴吉の生涯

四方 洋 著 あやべ市民新聞社 発行 清水弘文堂書房 発売 著者紹介 四方 洋 鶴吉を陰で支えながらも、その人物像はほとんど知られてこなかった妻・葉那 『今甦る葉那の人物像―グンゼ創業者・波多野鶴吉の妻―』 あやべ市民新 […]
「自然の恵み」の伝え方 生物多様性とメディア

日本環境ジャーナリストの会 編著 早稲田環境塾 協力 「生物多様性」「生態系サービス」をどう報道すればよいのか? 「生物多様性」「生態系サービス」という、まだ新しく、定義も充分に共有されていない概念を、ジャーナリストはど […]
地域環境戦略としての充足型社会システムへの転換

竹内恒夫 著 著者紹介 竹内恒夫 「この国の「半官製」、「商業主義」の「エコ」は既に飽和状態に達している」――環境庁・環境省で「エコ」関連施策、地球温暖化対策、廃棄物リサイクル政策などを担当し、現在は名古屋大学教授の筆者 […]
「野球移民」を生みだす人びと ドミニカ共和国とアメリカにまたがる扶養義務のネットワーク

窪田 暁 著 窪田 暁 著者プロフィール ドミニカ共和国の少年はどのように野球と出会い、海を越えアメリカを目指すのか? 外国出身メジャーリーガーを最も多く送りこんでいる(※)ドミニカ共和国。気鋭の若手人類学者が、ドミニカ […]
地球の善い一部になる。 環境共生経済への移行学

小林 光 著 アサヒ・エコ・ブックス No.38 著者紹介 小林 光 環境にいいものを買ったり、使ったり。 消費も、立派なエコになる。 地球温暖化の脅威は、年間7500億ドル規模の ビジネスチャンスでもある。 経済成長を […]
伝統野菜の今 地域の取り組み、地理的表示の保護と遺伝資源

香坂 玲/冨吉満之 著 アサヒ・エコ・ブックス No.37 著者紹介 香坂 玲 著者紹介 冨吉満之 日本の野菜を世界のブランドにするための入門書 日本各地の伝統野菜、地理的表示保護制度、知的財産権についても解説 今後、2 […]
新聞のある町 地域ジャーナリズムの研究

四方 洋 著 著者紹介 四方 洋 ローカル新聞26紙の現場に話を聞いた 全国紙もバフェットもほしがる「地域紙」は 今どうなっているのか? 「ブロック紙」「県紙」よりも 狭いエリアに密着する「地域紙」は 新聞退潮の時代でも […]
つぎの4冊